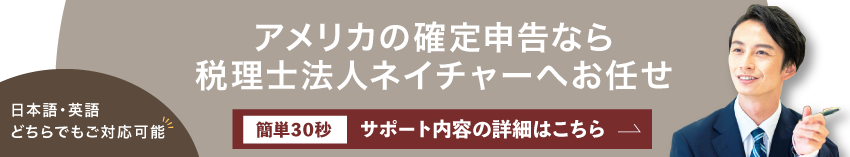「アメリカに不動産を持っているけど、子どもに渡すにはどうしたらいいんだろう?」
「海外に住む家族にお金を送ったら、贈与税はかかるのかな?」
海外に資産を持っていたり、海外在住の家族がいたりする方にとって、アメリカの贈与税は非常に複雑で、頭を悩ませる問題ではないでしょうか。
日本の贈与税のルールは知っていても、アメリカの税制は全く違うため、「気づかないうちに申告漏れになってしまった…」というケースも少なくありません。
問題の解決には、アメリカの贈与税の仕組みを正しく理解し、ご自身の状況に当てはめて考えることが重要です。
この記事では、国際税務の専門家である私たちが、アメリカの贈与税について、日本の税制との違いから、非居住者でも課税されるケース、さらには具体的な節税方法まで、分かりやすく徹底解説します。
この記事を読めば、アメリカの贈与税に関する不安が解消され、大切な資産を次世代に円滑に引き継ぐための第一歩を踏み出すことができます。
まずは確認!日米の贈与税の仕組みと最大の違い
日本とアメリカの贈与税は誰に課税されるかという根本的な考え方が異なります。
日本の贈与税が財産をもらった人(受贈者)に課税されるのに対し、アメリカの贈与税は財産をあげた人(贈与者)に課税されます。
日米の贈与税は誰に課税されるかが根本的に違う
- 日本の贈与税 : 原則として、財産をもらった人(受贈者)が納税義務を負います。
例えば、日本に住む親からアメリカに住む子が贈与を受けた場合、基本的には子が日本の贈与税を払う必要があります。
- アメリカの贈与税 : 原則として、財産をあげた人(贈与者)が納税義務を負います。
例えば、アメリカに住む親から日本に住む子が贈与を受けた場合、親がアメリカの贈与税を払う必要があります。
贈与者?受贈者?課税対象者を居住地で判断する仕組み
次に重要なのが居住地です。
国際的な贈与では、贈与者と受贈者のそれぞれの居住地(国籍ではない点に注意)によって、どこの国の贈与税が適用されるかが決まります。
日本の税務当局は受贈者の居住地を見て、アメリカの税務当局は贈与者の居住地を見る、というイメージです。
【知っておくべき3つのパターン】アメリカの贈与税が課税されるケース
「私は日本に住んでいるからアメリカの贈与税は関係ないだろう」と思われがちですが、実はそうとは限りません。
贈与者と受贈者の居住地、贈与する資産の種類によって、アメリカの贈与税が課税されるケースが大きく3つのパターンに分かれます。
パターン1 : 贈与者がアメリカ居住者、受贈者が日本居住者
贈与者であるアメリカ居住者にアメリカの贈与税が課税されます。
この場合、贈与者(アメリカ居住者)がアメリカのIRS(内国歳入庁)に申告・納税する義務があります。受贈者(日本居住者)は、日本の贈与税について考える必要がありますが、二重課税を避けるための規定もあります。
パターン2 : 贈与者が日本居住者、受贈者がアメリカ居住者
原則として、贈与者である日本居住者にアメリカの贈与税は課税されません。
しかし、贈与する資産がアメリカにある場合は注意が必要です。次のセクションで詳しく解説しますが、アメリカ国内の不動産や有価証券などを贈与する場合、非居住者であってもアメリカの贈与税の対象となることがあるため、注意が必要です。
パターン3 : 贈与者・受贈者ともに日本居住者
原則として、アメリカの贈与税は課税されません。しかし、贈与する資産がアメリカ国内にある場合は要注意です。
例えば、日本に住んでいる親が、同じく日本に住んでいる子どもに、アメリカにある不動産や銀行預金、株式などを贈与する場合です。
この場合、贈与者も受贈者も日本居住者なので、一見、アメリカの税金は関係ないように思えますが、贈与する資産がアメリカ国内にある特定財産であるため、アメリカの贈与税の対象となります。
贈与する資産が重要!アメリカの贈与税の対象となる資産とは
前述の通り、贈与者が非居住者であっても、アメリカの贈与税の対象となる資産があります。具体的には以下の3つです。
- アメリカ国内にある不動産
- アメリカ国内にある有形動産(例:家財、車など)
- アメリカ国内にある非上場株式
一方、以下のような資産は、贈与者が非居住者であればアメリカの贈与税の対象にはなりません。
- アメリカ国内にある預金(銀行預金など)
- アメリカ国内にある有価証券(上場株式や社債など)
- アメリカ国内にある生命保険契約
贈与する資産の種類によって、贈与税のルールが全く異なります。したがって、事前の確認なしに贈与を行うのは非常に危険です。
【専門家が解説】資産の種類で変わる評価方法と注意点
贈与税の計算では、贈与された資産の時価を正確に評価する必要があります。特に注意が必要なのが、非上場株式と不動産です。
- 不動産 : 時価の評価が難しく、専門家による鑑定が必要になる場合があります。
- 非上場株式 : 会社規模や業績、将来性などを加味した複雑な計算が必要となります。
- 銀行預金や上場株式 : 比較的容易に時価がわかりますが、為替レートや受け渡し日など、細かい注意が必要です。
贈与税ゼロも可能?非課税枠と賢い活用法
アメリカの贈与税には、日本の暦年贈与のような非課税枠があります。この制度をうまく活用すれば、贈与税を大幅に抑えることが可能です。
年間非課税額(暦年贈与)
年間で1人当たり1万8,000ドル(2024年現在)の贈与までは非課税です。
非課税額は、贈与者1人につき、贈与を受ける人1人に対して適用されます。
例えば、夫婦2人から子ども1人に贈与する場合、年間で最大3万6,000ドル(1万8,000ドル×2人)まで非課税で贈与できます。
生涯非課税額(控除額)と配偶者控除
贈与税と相続税を合わせた生涯の非課税額が設定されています。
- 生涯非課税額 : 2024年現在、1,361万ドルという莫大な非課税枠が設定されています。この金額は、贈与と相続を通じて生涯で使える控除額です。
- 配偶者控除 : 贈与者(アメリカ居住者)が、アメリカの市民権を持つ配偶者に贈与する場合、金額の上限なく非課税です。ただし、配偶者が市民権を持たない場合は、年間で18万5,000ドル(2024年現在)までが非課税となります。
非課税枠を最大限に活用する贈与プランニングのヒント
- 早期から計画的に贈与を始める:生涯非課税額があるとはいえ、年間非課税額を毎年コツコツと利用していくことで、大きな資産を非課税で移転させることが可能です。
- 配偶者控除をフル活用する: 配偶者がアメリカの市民権を持っている場合、この制度を最大限に活用することで、多額の資産を課税を受けることなく移転できます。
- 専門家に相談し、最適な方法を見つける: 贈与する資産や家族構成によって最適なプランは異なります。ご自身の状況に合わせたアドバイスを受けることが、節税の第一歩です。
【Q&A】アメリカの贈与税、申告・納税でよくある疑問
Q1 : 贈与税の申告はいつまでに、どうすればいい?
A : 贈与のあった年の翌年4月15日までに、IRSに申告する必要があります。
申告が必要となるのは、年間非課税額を超える贈与があった場合です。
申告にはForm 709という書類を使用します。
延長の申請を提出すると、期限は延長できますが、納税の延長はできません。
Q2 : 日本とアメリカで二重課税されることはない?
A : 日米間の贈与税については、二重課税を防止するための租税条約がありません。
しかし、日本の税制には外国税額控除という制度があり、一定の条件を満たせば、海外で支払った税金を日本の税金から差し引くことが可能です。
ただし、これは非常に複雑な計算が必要となるため、専門家のサポートが不可欠です。
Q3 : 申告を忘れたらどうなる?
A : 無申告や過少申告の場合、重いペナルティが課される可能性があります。
意図的な脱税とみなされると、刑事罰の対象となることもあります。
「知らなかった」では済まされないのが国際税務の怖さです。
【実際の事例】税理士法人ネイチャーが解決した贈与税トラブル
「うちの場合、どうなるの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、実際に税理士法人ネイチャーにご相談いただいた事例を2つご紹介します。
事例1 : アメリカの投資口座を子どもに名義変更しようとしたら…
- ご相談内容 : 日本在住のA様(70代)は、アメリカの証券会社に長年保有していた投資口座を、同じく日本在住の子どもに贈与したいと考えていました。
- 問題点 : A様は「年間1万8,000ドルの非課税枠内で少しずつ贈与すればいい」と考えていましたが、この口座は名義変更ができない仕組みでした。そのため、一度解約・送金する必要があり、多額の贈与が一度に発生する可能性がありました。
- 当社の解決策 : アメリカの銀行や証券会社に直接問い合わせを行い、口座の種類や名義変更の可否を詳細に調査しました。結果、口座の特性を理解した上で、最も税負担が少なく、手間もかからない贈与の方法を提案しました。具体的には、米ドルを日本に送金する際の注意点や、日本の贈与税の申告方法まで含めた総合的なアドバイスを提供し、無事に贈与手続きを完了させました。
事例2 : 日本の不動産をアメリカに住む親族に贈与したいが…
- ご相談内容 : 日本に住むB様は、所有する日本のマンションを、アメリカに住む妹に贈与したいと考えていました。
- 問題点 : 「贈与は贈与者と受贈者の両方が海外に住んでいるわけではないので大丈夫だろう」と考えていましたが、妹がアメリカ居住者のため、妹に日本の贈与税が課税されます。さらに、不動産贈与には登記の手続きや評価方法など、通常の贈与とは異なる複雑なステップが必要です。
- 当社の解決策 : 妹様が日本の贈与税を申告・納税する必要があることをご説明し、日本の税理士として申告業務をサポート。さらに、将来的に妹様がその不動産を売却する際の税金(譲渡所得税)も見据えたアドバイスを行い、税金対策と手続きの両面からサポートしました。
贈与と相続、どちらが有利?資産承継の専門家が教えるベストな選択
目先の贈与税ばかりに気を取られて、将来の相続を忘れてはいけません。
贈与と相続は、どちらか一方を選ぶものではなく、組み合わせて考えるべきものです。
なぜ贈与と相続を一体で考えるべきなのか
贈与税と相続税は、生涯の資産承継全体を考える上で、車の両輪のようなものです。
アメリカには贈与税と相続税を合わせた生涯非課税額があるため、贈与で非課税額を使ってしまうと、将来の相続で使える非課税額が減ってしまいます。
つまり、どの資産を、どのタイミングで、どの方法で、誰に引き継ぐかという長期的な戦略が不可欠なのです。
国際税務における贈与と相続の最適な組み合わせ
- 少額資産は生前贈与で : 年間1万8,000ドルの非課税枠を毎年活用し、少しずつ贈与を進める。
- 高額資産は相続で : 将来の相続時精算課税制度の活用や、相続税申告時の評価方法の検討など、相続の専門家と連携して対策を練る。
複雑な国際税務は専門家に相談を!
この記事で解説した内容は、あくまで一般的な情報です。
実際の税務手続きでは、個々の状況(居住地、市民権、資産の種類、家族構成など)によって、適用されるルールや注意点が大きく異なります。
- 「自分のケースではどうなるの?」
- 「申告書類の書き方がわからない」
- 「将来の相続まで見据えた最適なプランを相談したい」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、私たち税理士法人ネイチャーにご相談ください。
資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。
お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。
豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。