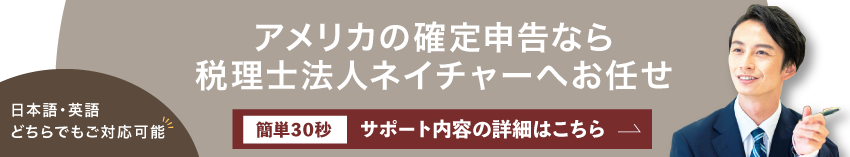「ドイツに住んでいる親族から、財産を相続することになった…」
そんなとき、「一体いくら税金がかかるんだろう?」という疑問と、「手続きが複雑そうで、何から手をつけていいか分からない」という不安が頭をよぎるのではないでしょうか。
特に、日本とドイツの二つの国の税金がかかるとなると、「二重に税金を払うことになったらどうしよう」と、さらに心配は大きくなります。
しかし、ご安心ください。この記事では、これまで数多くの国際相続のケースを解決してきた私たちが、ドイツの相続税の仕組みを分かりやすく解説します。この記事を読めば、やるべきことが明確になり、漠然とした不安から解放され、安心して次のステップに進めるでしょう。
まずは知っておきたい!ドイツの相続税の基本ルール
ドイツの相続税は、日本の相続税と大きく異なります。まずは、基本的な仕組みから見ていきましょう。
ドイツの相続税は「遺産取得課税方式」
日本の相続税は遺産全体に対して課税されますが、ドイツでは遺産を取得した人(相続人)が受け取った財産に対して課税される遺産取得課税方式が採用されています。つまり、受け取る人それぞれに税金が計算されるということです。
【要注意】贈与税と相続税はセットで考えられる
ドイツの相続税を考える上で、絶対に忘れてはならないのが、生前贈与との関係です。ドイツでは、相続発生前10年以内に行われた贈与が、相続財産と合わせて課税対象となります。
日本でも同様のルールがありますが、日本の加算期間は現在7年間(2024年1月より順次延長)であるのに対し、ドイツは10年と長いため、注意が必要です。
家族関係で大きく変わる基礎控除と税率
ドイツの相続税には、日本と同様に基礎控除が設けられています。これは、一定額まで相続税がかからないという制度で、誰が相続するかによって大きく金額が変わります。
|
相続人の続柄 |
基礎控除額 |
| 配偶者 | 50万ユーロ |
| 子 | 40万ユーロ |
| 孫 | 20万ユーロ |
| 兄弟姉妹 | 2万ユーロ |
※2024年9月時点の目安です。実際の控除額や税率は変動する可能性があります。
基礎控除額を超えた部分に、以下の税率が適用されます。ドイツの税率は日本の55%と比べて低く設定されており、最も低い税率は7%から始まります。
|
控除後の課税対象額 |
税率 |
| 7万5,000ユーロ以下 | 7% |
| 7万5,000ユーロ~30万ユーロ | 11% |
| 30万ユーロ~60万ユーロ | 15% |
| 60万ユーロ~600万ユーロ | 19% |
| … | … |
ドイツでは、相続する財産の額だけでなく、相続人と被相続人の関係性によって税額が大きく変わるのが特徴です。
【日本在住者向け】ドイツと日本の相続税「二重課税」はこうして防ぐ
国際相続で最も心配なのが二重課税です。多くのケースでは二重に税金を払う必要はありません。その仕組みを解説します。
国際相続で最も重要な「納税義務者」の判定
日本とドイツのどちらの税法が適用されるかは、被相続人(亡くなった方)と相続人(財産を受け取る人)の住所や国籍によって決まります。これを納税義務者の判定といいます。
- 日本に住所がある人(あなた)
原則として、日本の相続税法が適用され、全世界の財産(ドイツの財産も含む)が課税対象となります。 - ドイツに住んでいた被相続人(亡くなった方)
原則として、原則として、ドイツでは被相続人の居住地に基づいて課税範囲が決まるため、全世界の財産が課税対象となります。
つまり、日本に住むあなたが、ドイツに居住していた親族から財産を相続する場合、日本とドイツの両方で相続税が課される可能性があります。このため、二重課税が生じることになるのです。
二重課税を確実に防ぐ「外国税額控除」の仕組み
二重課税を防ぐために、日本の税法には外国税額控除という制度が設けられています。
海外で支払った相続税がある場合、その分を日本の相続税から差し引ける制度です。
簡単に言うと、ドイツで支払った相続税の金額を、日本の相続税から差し引くことで、結果的に二重で税金を払う事態を避けることができます。この制度を正しく適用することで、安心して手続きを進めることができます。
ドイツ相続で失敗しないための注意点と具体的な手続きの流れ
国際相続は、日本の相続とは異なり、思わぬ落とし穴があります。ここでは、私たちが過去に経験したトラブル事例と、スムーズな手続きのためのステップをご紹介します。
実際のトラブル事例から学ぶ!よくある落とし穴
事例1:ドイツの不動産評価が難しく、申告に手間取ったケース
ドイツにある不動産を相続したお客様の事例です。不動産の評価方法が日本とは異なり、評価額の算出に時間がかかりました。評価が遅れたことで、日本の相続税申告に間に合わない可能性が出てきましたが、現地の専門家と連携し、早急に評価を完了させることで、無事に申告期限内に手続きを完了することができました。
事例2:海外の銀行口座の凍結解除に時間がかかったケース
ドイツの銀行に預金があったお客様の事例です。被相続人の死亡が確認されると、銀行口座は一時的に凍結されます。解除には、現地の法律に基づいた特定の書類(相続人の証明書など)が必要となりますが、言葉の壁や書類の不備により、手続きが停滞してしまいました。専門家が代行することで、スムーズな書類のやり取りが可能となり、早期に口座の凍結が解除されました。
これらの事例からもわかるように、国際相続は日本の相続とは全く異なる知識と実務経験が求められます。
スムーズな手続きのための3ステップ
- 相続財産の全体像を把握する
まずは、ドイツ国内にどのような財産(銀行預金、不動産、株式など)があるかをリストアップしましょう。 - 日本とドイツ、どちらで申告が必要か判断する
あなたの住所や被相続人の住所などから、日本とドイツ、どちらでの申告が必要か判断します。 - 専門家(国際税務に強い税理士)に相談する
上記2つのステップは、専門家と一緒に行うことをおすすめします。
複雑なドイツの相続は専門家に任せるべき3つの理由
「自分でやれば費用が抑えられるのでは?」とお考えの方もいるかもしれません。しかし、国際相続の複雑さやリスクを考えると、専門家に依頼するメリットは計り知れません。
1.複雑な税務計算と申告書類作成をミスなく行える
日本とドイツ、それぞれの税法を正確に理解し、複雑な計算を行うことは、一般の方には非常に困難です。また、申告書類の作成には専門的な知識が不可欠であり、少しのミスが追徴課税につながるリスクがあります。
2.現地専門家との連携により、手続きをスムーズに進められる
国際税務に特化した税理士は、現地の税理士や弁護士とのネットワークを持っています。これにより、ドイツでの手続きや書類のやり取りもスムーズに進めることができ、時間と労力を大幅に節約できます。
3. お客様の状況に合わせた最適な節税対策を提案できる
専門家は、お客様一人ひとりの財産状況や家族構成に合わせて、合法的な範囲で最も有利な節税方法を提案できます。例えば、ドイツの基礎控除を最大限活用する方法や、外国税額控除を正確に計算する方法など、専門的な知見が必要です。
まとめ:ドイツの相続は安心・確実な専門家への相談が解決への近道
ドイツの相続税は、日本の相続税とは異なる点が多く、手続きも複雑です。「二重課税になるのでは?」という不安は、外国税額控除の仕組みを理解すれば解消できます。
しかし、その手続きを正確に行うには、国際税務の専門的な知識が不可欠です。
私たち税理士法人ネイチャーは、国際相続の経験が豊富であり、お客様の不安に寄り添い、安心・確実な相続手続きをサポートします。
資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。
お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。
豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。