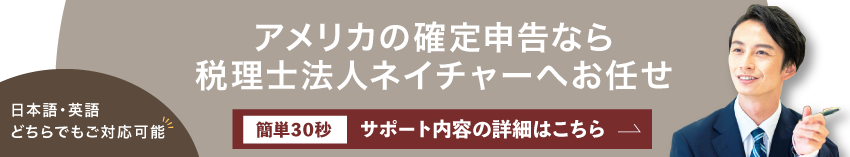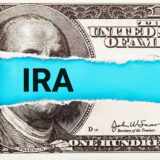「アメリカで頑張っている息子に、マイホームの頭金を援助してあげたい」
「娘夫婦の生活の足しになるように、まとまったお金を渡したい」
大切なお子様を想うそのお気持ち、痛いほどよく分かります。しかし、その想いを形にする生前贈与が、国境を越えた途端に非常に複雑な税金問題を引き起こす可能性があることをご存知でしょうか?
良かれと思って行った生前贈与が、知識不足から思わぬ高額な税金やペナルティに繋がってしまったケースは少なくありません。
この記事では、国際税務のプロである私たちが、アメリカ在住のお子様へ生前贈与をお考えの日本の親御様に向けて、知っておくべき税金の知識と手続きの全てを、どこよりも分かりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が解消されているはずです。
アメリカ在住の子への生前贈与、ポイントは日米の「贈与者」と「受贈者」の立場!
日本の親からアメリカ在住の子への生前贈与では、日本の贈与税とアメリカの贈与税(Gift Tax)、両方のルールを理解する必要があります。どちらの税金が、誰にかかるのかは、お金をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の状況によって決まります。
日本の贈与税がかかるケース
日本の贈与税は、原則として日本に住所がある人から財産をもらった全ての人にかかります。
つまり、日本の親御様(贈与者)が日本にお住まいである以上、アメリカ在住のお子様(受贈者)へ贈与した場合、原則として日本の贈与税の課税対象となります。
年間110万円の基礎控除(暦年贈与)を超える部分について、申告と納税が必要です。
アメリカの贈与税(Gift Tax)がかかるケース
一方、アメリカの贈与税は、日本とは考え方が大きく異なります。ポイントは以下の通りです。
- 支払うのはあげた人(贈与者):
アメリカでは、贈与税は原則として財産をあげた側が支払います。もらった側(お子様)に納税義務は発生しません。 - 贈与者が米国市民・居住者でなければ、米国内の資産でない限り課税されない:
日本の親御様がアメリカの市民や永住権保持者でない場合、日本にある現金(預金)をお子様の米国の口座に送金する、という形であれば、アメリカの贈与税(Gift Tax)はかかりません。
つまり、多くのケースでは、贈与する親御様が日本にお住まいであれば、アメリカの贈与税の心配は不要ということになります。
あなたの場合、日米どちらの税金がかかる?
多くの方が該当する贈与者(親)が日本居住、受贈者(子)がアメリカ居住のケースをまとめました。
| 贈与する財産 | 日本の贈与税 | アメリカの贈与税(Gift Tax) |
| 日本にある現金・預金 | 課税される | 課税されない |
| 日本にある不動産 | 課税される | 課税されない |
| アメリカにある不動産・証券 | 課税される | 課税される |
※受贈者(子)が日本国籍を持っているか、過去の居住歴などにより、日本の課税範囲は変わる可能性があります。
ポイント:多くのケースでは日本の贈与税に注意すれば問題ありません。しかし、後述するアメリカ側の報告義務を怠ると重い罰則があるため、注意が必要です。
知らないと損!アメリカの生前贈与に関する3つの非課税制度
「アメリカの贈与税はかからないのか、よかった」と安心するのはまだ早いです。お子様が贈与を受け取った際に、アメリカの税務当局(IRS)への報告が必要になる場合があります。その際に重要になるのが、アメリカの非課税制度の知識です。
アメリカには、贈与に関する非常に手厚い非課税制度があります。
1. 年間非課税枠(Annual Exclusion):年間約280万円まで非課税
アメリカには、1人あたり年間で一定額までなら、贈与税の申告も納税も不要という非課税枠があります。
- 2024年の金額:1万8,000ドル
- 2025年の金額:1万8,000ドル (※2024年11月時点での予測。インフレにより変動の可能性あり)
1万8,000ドルずつ、合計3万6,000ドル(約558万円)を贈与することも可能です。
2. 生涯非課税枠(Lifetime Gift and Estate Tax Exemption):約20億円という巨額な枠
もし年間非課税枠を超える贈与をしても、すぐに税金が発生するわけではありません。アメリカには、生前贈与と遺産(相続)を合算した生涯非課税枠という、巨大な控除枠が存在します。
- 2024年の金額:1,361万ドル (1人あたり)
- 2025年の金額: インフレによりさらに増額の見込み
日本円で約21億円という、非常に大きな金額です。
年間非課税枠を超えた贈与は、この生涯非課税枠から差し引かれていき、枠を使い切るまでは贈与税の支払いは発生しません(ただし、申告は必要です)。
3. 教育費・医療費の直接支払い:目的が決まっていれば非課税
お子様やお孫さんの教育費(学費)や医療費を支払う目的であれば、上記の非課税枠とは別枠で、全額非課税になる制度があります。
ポイント:この制度を利用するには、親御様がお子様本人に現金を渡すのではなく、学校や病院に直接支払う必要があります。
【ケース別】アメリカへの生前贈与、具体的な手続きと申告の流れ
では、実際に贈与を行う場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。よくある3つのケースで見ていきましょう。
※ここでは、贈与者である親は日本居住、受贈者である子はアメリカ居住(米国市民や永住権保持者)と仮定します。
ケース1:年間110万円以内で現金を贈与する場合
日本の贈与税の基礎控除(110万円)の範囲内で行う、最もシンプルなケースです。
- 日本の親(贈与者)がやること:
- 税務申告: 不要です。
- 手続き: 銀行で海外送金の手続きを行います。
- アメリカの子(受贈者)がやること:
- 税務申告: 不要です。(アメリカの年間非課税枠1万8,000ドルも下回るため)
【実務上のアドバイス】
贈与の証拠として、誰が誰に、いつ、いくら贈与したかを明記した贈与契約書を作成しておくことをお勧めします。後々の税務調査などで、単なる親子間のお金の貸し借りではないことを証明するために有効です。
ケース2:年間500万円の現金を贈与する場合
日本の基礎控除110万円を超えるため、申告が必要です。
- 日本の親(贈与者)がやること:
- 税務申告: 必要です。贈与があった翌年の2月1日~3月15日の間に、日本の税務署へ贈与税の申告と納税を行います。
- 計算例:(500万円 – 110万円) × 20% – 25万円 = 53万円 の贈与税がかかります。(特例贈与の場合)
- アメリカの子(受贈者)がやること:
- 税務申告: 原則不要です。前述の通り、贈与税を支払うのは日本にいる親であり、アメリカにいる子ではありません。ただし、後述するForm 3520による報告義務が発生する可能性があります。これは絶対に忘れてはいけません。
ケース3:日本の不動産を贈与する場合【専門家への相談が必須】
このケースは非常に複雑で、専門家のサポートなしに進めるのは極めて危険です。
- 発生する税金:
- 日本の贈与税: 土地や建物の評価額を基に課税されます。
- 日本の不動産取得税・登録免許税: 不動産の名義変更に伴い発生します。
- 注意すべき点:
- 日米での評価額の違い: 日本の路線価評価と、アメリカの時価評価では金額が大きく異なり、将来お子様がその不動産を売却した際の税額に大きな影響を与えます。
- 手続きの煩雑さ: 司法書士と連携した登記手続きなど、専門的なプロセスが必要です。
不動産の贈与をお考えの場合は、手続きを開始する前に、必ず日米の税務に精通した税理士にご相談ください。
親子で確認すべき生前贈与の3つの注意点
税金の知識だけでは万全ではありません。国際税務の現場でよく見る、陥りがちな落とし穴を3つご紹介します。
注意点1:受贈者(子)の報告義務|Form 3520の提出漏れは高額罰金の対象に
アメリカ在住のお子様は、外国(日本)の個人から年間で10万ドル(約1,550万円)を超える贈与を受け取った場合、アメリカの税務当局(IRS)に「Form 3520」という書類を提出して、「こういう贈与を受け取りました」と報告する義務があります。
- これは納税ではありません。あくまで報告です。
- しかし、この報告を怠ったり、遅れたりすると、贈与額の5%(最大で25%まで)という非常に高額な罰金(ペナルティ)が科される可能性があります。
贈与する親御様は、贈与額が10万ドルを超える場合は、必ずお子様にこの報告義務があることを伝え、忘れないように念押ししてあげてください。
注意点2:「暦年贈与」の感覚は危険!日米の制度の違いを理解する
日本では「毎年110万円ずつ」贈与する暦年贈与が一般的な節税策として知られています。しかし、この感覚のままアメリカの制度を見ると、思わぬ誤解を生むことがあります。
- 日本の暦年贈与: 主に相続税対策として、長期的に資産を移転させる目的で行われます。
- アメリカの年間非課税枠: そもそも生涯非課税枠が非常に大きいため、相続税対策としての重要度は日本ほど高くありません。
「アメリカの非課税枠は1万8,000ドルもあるから、毎年ギリギリまで贈与しよう」と考える必要は必ずしもありません。ご自身の資産状況と、贈与の目的に合わせて計画を立てることが重要です。
注意点3:将来の相続まで見据えたプランニングを
今回の生前贈与が、将来の相続全体にどのような影響を与えるかを考える視点も大切です。
例えば、日本の相続税対策として生前贈与を進めても、お子様がアメリカの遺産税(Estate Tax)の対象者である場合、そちらの対策も別途必要になるかもしれません。
生前贈与は、相続という大きなパズルの一つのピースに過ぎません。ぜひ、全体像を見渡した上で、最適な一手をご検討ください。
「うちの場合はどうなるの?」専門家に相談すべき3つのケース
ここまで一般的な解説をしてきましたが、「自分の場合はどうなのだろう?」と不安に思われる方も多いでしょう。特に、以下のようなケースに当てはまる方は、自己判断せず専門家にご相談されることを強く推奨します。
ケース1:贈与額が高額(数千万円以上)になる
日本の贈与税額も高額になり、特例制度の活用など、より有利な方法を検討すべきです。また、お子様のForm 3520の報告義務も確実に発生します。
ケース2:贈与する資産が不動産や株式である
現金と異なり、評価額の算定や名義変更手続き、将来の売却時の税金など、考慮すべき論点が格段に増え、複雑化します。
ケース3:贈与者・受贈者の状況が複雑(米国市民、永住権保持者など)
もし、贈与する親御様自身が米国のグリーンカードをお持ちであったり、お子様が米国市民であったりすると、適用される税法が全く異なってきます。この場合、アメリカの贈与税が直接課税される可能性が高まります。
まとめ|アメリカへの生前贈与は、計画的な準備と専門家の活用が成功のカギ
アメリカ在住のお子様への生前贈与は、愛情を形にする素晴らしい行為です。しかし、そのプロセスには日米両国の税法が複雑に絡み合います。
成功のポイントは以下の3つです。
- 日米の税金の基本を理解する: まずは日本の贈与税、そしてアメリカの報告義務を正しく知ること。
- 親子で情報を共有する: 特に、お子様が負うことになるアメリカでの報告義務(Form 3520)について、必ず事前に伝えておくこと。
- 少しでも不安があれば専門家に相談する: 自己判断で進めて後で問題が発覚すると、取り返しがつかないケースもあります。
私たち税理士法人ネイチャーは、日米間の国際税務、特に生前贈与や相続に関する豊富な経験と実績を有しています。お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、ご家族にとって最も幸せな形で資産を繋ぐお手伝いをさせていただきます。
資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。
お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。
豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。