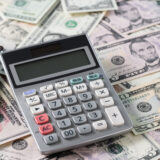RSU(譲渡制限付株式)を付与され、その価値がどんどん上がっていくのを見て「うれしい!」と感じた後、こう思っていませんか?
「…でも、これって結局、いくら税金がかかるんだろう?」
RSUは、いわば突然のボーナスのように、あなたの資産を大きく増やしてくれる素晴らしい仕組みです。しかし、その裏側には、ちょっと複雑な税金のルールが隠されています。
この記事は、RSUの税金に不安を感じているあなたのために、現役税理士である私たちがその仕組みから計算方法、そして誰もが知りたい節税対策まで、徹底的に分かりやすく解説します。
読後はきっと、モヤモヤしていた頭がスッキリして、安心して次の行動に移せるはずです。一緒にRSUの税金の正体を探っていきましょう。
RSUの仕組みを5分で理解する|税金はいつかかる?
RSU(譲渡制限付株式)とは?ストックオプションとの違い
RSU(Restricted Stock Unit)とは、会社が従業員に「将来、一定の条件を満たしたら、自社の株式を無償で渡します」と約束する報酬制度です。この一定の条件とは、通常、「〇年間継続して勤務すること」といった勤続年数です。
RSUは、いわゆるストックオプションと混同されがちですが、決定的な違いがあります。
| 項目 | RSU(譲渡制限付株式) | ストックオプション |
|---|---|---|
| 受け取るもの | 株式そのもの | 株式を特定の価格で購入する権利 |
| 従業員の費用負担 | 無償(なし) | 有償(権利行使価格の支払いが必要) |
| 権利確定/行使時の価値 | 株価が0でなければ必ず価値がある | 株価が行使価格を上回らないと利益が出ない |
RSUの課税タイミングは2回!「権利確定時」と「売却時」
RSUにかかる税金は、主に2つのタイミングで発生します。この2つを混同すると、税金計算で大きな間違いをしてしまうので注意が必要です。
最初の課税タイミングは、勤続年数などの条件を満たして株式を正式に受け取る権利確定(Vesting)時です。この時、受け取った株式の時価があなたの給与所得とみなされ、所得税や住民税の対象となります。
そして2つ目のタイミングが、その株式を市場で売却(Sale)する時です。この時には、権利確定時の株価からの値上がり益が譲渡所得として課税されます。
例えば、1株1,000円の時に100株の権利が確定し(給与所得10万円)、その後株価が2,000円に上昇した時に全株を売却したとすると、差額の10万円((2,000円-1,000円)×100株)が譲渡所得として課税されるという二段階の仕組みになっています。
源泉徴収される税金と、確定申告が必要なケース
外資系企業の場合、権利確定時に会社が株式を一部売却して税金を源泉徴収してくれるケースが多いです。しかし、源泉徴収はあくまで概算であり、売却時の税金は対象外です。
そのため、以下のケースではご自身で確定申告が必要となります。
- RSU売却によって利益(譲渡所得)が出た場合
- 海外のグループ会社からRSUが付与され、源泉徴収がされていない場合
- 年末調整で控除しきれない所得控除がある場合
RSUの税金はいくらになる?計算方法を徹底解説RSUにかかる税金が給与所得と譲渡所得の2種類あることを理解したところで、次にそれぞれの具体的な計算方法を見ていきましょう。
所得の種類によって税率や計算方法が全く異なるため、その違いをしっかりと理解することが重要です。
RSU権利確定時の税金(給与所得)の計算方法
権利確定時にかかる税金は、給与所得とみなされるため、あなたの年収(給与所得)に合算されて、所得税の累進課税が適用されます。
所得税の税率は、所得が上がるほど税率も高くなる「累進課税」です。例えば、課税所得が1,000万円を超えると税率は33%に、1,800万円を超えると40%になります。さらに住民税(約10%)も加わるため、手取りが大きく目減りする可能性があります。
所得税+住民税+社会保険料
RSUの権利確定による所得は給与所得とみなされ、税金だけでなく社会保険料(健康保険・厚生年金)の算定基礎にも含まれます。
具体的には、権利確定月の給与にRSUの価値が上乗せされる(賞与扱いなど)ため、その後の社会保険料が1年近くにわたって大幅に増額される可能性があります。このインパクトは非常に大きいため、手取り額を考える上で絶対に忘れてはならないポイントです。
RSU売却時の税金(譲渡所得)の計算方法と注意点
株式を売却して得た利益は、譲渡所得として課税されます。
譲渡所得 = 売却時の株価 – 権利確定時の株価
この譲渡所得にかかる税金は、所得税15%と住民税5%を合わせた、合計20.315%(復興特別所得税を含む)の申告分離課税です。
給与所得とは合算されず、この税率で一律に課税されます。この「申告分離課税」は、給与所得の累進課税と違い、税率が変わらないのが特徴です。
【注意点】
譲渡所得の計算では、証券会社から送られてくる特定口座年間取引報告書を必ず確認しましょう。ここには、売却価格や取得価格(権利確定時の株価)が記載されています。
【ケーススタディ】RSUを付与されたAさんの納税額をシミュレーション
Aさんのプロフィール:
- RSU付与数:1,000株
- 権利確定時の株価:2,000円
- 権利確定時の源泉徴収額:40万円
- 売却時の株価:3,000円
Aさんが1,000株のRSUを付与された具体的なケースで見ていきましょう。
まず、株価が2,000円の時に1,000株全ての権利が確定(Vesting)したとします。この瞬間、200万円(2,000円×1,000株)がAさんの給与所得に上乗せされ、その年の所得税・住民税が計算されます。Aさんの場合、所得が増えることで税率が上がり、追加で数十万円の税金が発生する可能性があるので注意が必要です。
その後、Aさんは株価が3,000円になったタイミングで全株を売却(Sale)しました。この時、権利確定時の株価2,000円からの値上がり益である(3,000円-2,000円)×1,000株の100万円が譲渡所得となります。この利益に対し、一律20.315%の税率で203,150円の税金が課され、確定申告で納める必要があります。
このように、RSUでは権利確定時と売却時の2回にわたって税金がかかることを理解しておくことが重要です。
【知らないと損】RSUで手元に残る金額を増やす3つの税金対策
RSUの税金はルールに則って正しく納める必要がありますが、いくつかの対策を知っておくことで、手元に残る金額を合法的に増やすことが可能です。
ここでは、多くの人が見落としがちな納税額を抑えたりキャッシュフローを改善したりするための代表的な3つの対策をご紹介します。
対策1:あえて売却タイミングをずらす戦略
RSUの税金を考える上で、実は売却タイミングが非常に重要です。特に、権利確定した年の年末に売却するよりも、翌年の年初に売却することで、納税のタイミングを1年間遅らせることができます。
例えば、2025年12月に権利確定・売却した場合、確定申告は翌年の2026年3月に行い、納税も同じく2026年に行います。
しかし、権利確定した株式を2026年1月に売却した場合、確定申告は2027年3月となり、納税までの期間を1年延ばすことが可能です。
これにより、納税資金を準備する時間的余裕ができ、その間の資金を運用に回せるでしょう。
対策2:ふるさと納税を活用した効果的な節税術
RSUの権利確定により、課税所得が大幅に増えることになります。この増えた所得に対して、ふるさと納税の控除上限額を再計算し、最大限活用することで、実質的な納税額を抑えることができます。
ふるさと納税は、所得が増えるほど控除上限額も増える仕組みです。RSUが付与された年は、普段よりも多めにふるさと納税を行うことで、美味しい返礼品を受け取りながら、節税効果を享受できるのです。
対策3:iDeCoやNISAをフル活用する
RSUによって一時的に所得が増える年は、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)といった制度を最大限に活用する絶好のチャンスです。
まずiDeCoは、掛金の全額が所得控除の対象となるため、RSUの権利確定によって増えた課税所得を直接的に圧縮できる非常に有効な節税策です。
一方のNISAでは、権利確定したRSUを一度売却し、その資金でNISA口座内で金融商品を買い直すことでその後の値上がり益(譲渡所得)や配当を非課税にできます。将来の株価上昇を期待する場合は、このNISA口座での買い直しを検討する価値があります。
RSU確定申告のやり方とよくある「落とし穴」
RSUの税金の仕組みを理解したら、最後は実践編となる確定申告です。RSUの確定申告は、通常の年末調整とは異なり、ご自身で手続きが必要になるケースがほとんどです。
この章では、申告が必要になる具体的なケースから、税務調査で指摘されやすいポイントまで失敗しないための知識を解説します。
確定申告が必要になるケースと不要なケース以下のケースでは確定申告が必要です。
【申告が必要なケース】
- RSUを売却して利益が出た場合
- 給与所得の合計が2,000万円を超える場合
- 給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合
- 海外のグループ会社からRSUが付与され、源泉徴収が行われていない場合
用意すべき書類と具体的な申告書の書き方
申告には主に以下の書類が必要です。
- 源泉徴収票
- 特定口座年間取引報告書(株式の売却で譲渡所得がある場合)
- RSU権利確定時の評価額を証明する書類(会社が発行する書類など)
申告書は、国税庁のサイトで作成するか、税理士に依頼するのが一般的です。
【失敗談から学ぶ】税務調査で指摘されやすい3つのポイント
税務調査で指摘されやすいポイントは、主に3つあります。
最も多いのが、確定申告が必要だと知らなかったという単純な申告漏れです。特に海外親会社から付与されるRSUは源泉徴収されないため、税務署から指摘があるまで気づかないケースが後を絶ちません。
次に、申告はしたものの、売却益(譲渡所得)を計算する際の取得価格(権利確定時の株価)を間違えてしまうケースです。これは税務調査で必ずチェックされるポイントであり、誤りがあると追徴課税につながります。
最後に、海外で源泉徴収された税額を日本の税額から差し引ける外国税額控除の適用を忘れるケースです。これでは、本来払う必要のない税金を二重に納めてしまうことになります。
国際税務の専門家が解説!海外RSUで特に注意すべきこと
外資系企業にお勤めの場合、RSUは海外の親会社から付与されることがよくあります。この場合、日本の税制だけでなく、その国の税制も考慮する必要があり、非常に複雑になります。
特に、海外で源泉徴収された税金がある場合は、日本と海外での二重課税を避けるために、確定申告で外国税額控除を正しく適用することが不可欠です。多くの国とは租税条約が結ばれており、これに基づき適切に申告すれば、余分な税金を払う必要はありません。
また、RSUの権利が確定するタイミングで海外赴任中だったり、日本へ帰国した直後だったりすると、日本の居住者か非居住者かという判定が複雑になり、課税関係が大きく変わることがあります。このような特殊なケースでは、必ず国際税務に強い税理士にご相談ください。
RSUの「出口」戦略:納税後の資産はこう守り、増やす
RSUで大きな利益を得て、多額の税金を納めた後、残った資金をどう活かすかは非常に重要な問題です。
納税資金確保後の「余剰資金」の賢い使い方
多くの人は、RSUを売却して納税資金を確保するところで満足してしまいます。しかし、そこで得た資金を銀行に預けたままでは、せっかくの資産がインフレで目減りするリスクがあります。
金融資産の専門家が考える、RSU資産の運用ポートフォリオ
納税後のお金は、守りと攻めの両方を意識した運用が大切です。
まず守りの資産とは、納税のために確保しておいた資金や当面の生活費などのようなリスクに晒すべきではないお金のことです。これらは安全な預金などで確実に保持します。
その上で、余剰資金を攻めの資産として長期的な成長を目指します。例えば、個別企業の成長に期待する株式投資や世界経済全体に分散投資する投資信託などです。どのような配分にするかは、ご自身の年齢やリスク許容度に応じて決めることが重要です。
RSUで得たお金は、未来の資産です。税金を支払った後こそ、その価値を最大限に高める戦略を立てましょう。
複雑なRSUの税金はプロに相談するのが一番の近道
ここまでRSUの税金について解説してきましたが、特に海外RSUが絡む場合、自身ですべてを完璧に申告するのは非常に難しい作業です。
この章では、どのような方が税理士に相談を検討すべきか、そして私たち専門家が提供できるサポートについてご紹介します。
こんな人は税理士への相談を検討しよう
- RSUの確定申告が初めてで、やり方が分からない。
- 海外のRSUが付与されており、国際税務の知識が必要。
- RSUの額が大きく、納税資金の確保や節税対策に不安がある。
- 本業が忙しく、確定申告に時間をかけられない。
RSUの相談なら【税理士法人ネイチャー】にお任せください
私たち税理士法人ネイチャーは、これまで数多くのRSUに関するご相談をお受けし、円滑な確定申告と最適な税金対策をサポートしてきました。
特に、金融資産や国際税務に強みを持つため、RSUの税金計算はもちろん、納税後の資産運用まで含めた総合的なアドバイスを提供できます。
RSUの税金対策でお悩みの方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
まとめ:RSUの税金対策は「知る」ことから
RSUの税金は、その仕組みを一度理解してしまえば、決して怖いものではありません。
今回の記事で、RSUの税金が「権利確定時」と「売却時」の2回に分けてかかること、そして納税額を減らすための効果的な対策があることをご理解いただけたかと思います。
一番の失敗は、分からないからと放置してしまうことです。今日この記事を読んだあなたは、すでにその第一歩を踏み出しました。
RSUで得たあなたの資産を最大限に守り、増やしていくために、ぜひこの情報を活用してください。
資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。
お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。
豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。