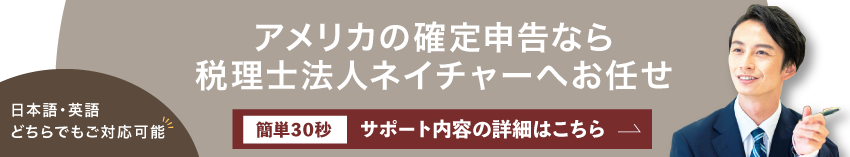故人がアメリカ国籍をお持ちだった場合、相続手続きにおいて、日本の相続税に加え、アメリカの遺産税(Estate Tax)が関係することがあります。
日米それぞれの税制は、課税の考え方や手続きが異なるため、相続の状況によっては、両国の税務を整理して検討する必要があります。本記事では、アメリカ国籍者の相続において一般的に問題となりやすい点を中心に、基本的な考え方や実務上の留意点を整理します。
基礎知識:日本の相続税とアメリカ遺産税の基本的な違い
被相続人(亡くなった方)がアメリカ国籍の場合、まず理解しておきたいのが、日本とアメリカにおける課税の考え方の違いです。
日本の相続税:誰が相続したかに着目する相続人課税
日本の相続税は、遺産を受け取った人(相続人)の視点で課税を判断します。
| 課税の判断基準 | 相続人の住所や居住歴、国籍など |
| 基礎控除 | 基礎控除 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
アメリカの遺産税:遺産全体に着目する遺産課税
アメリカの遺産税は、遺産を残した人(被相続人)の視点で課税を判断します。遺産の総額に対して税金がかかり、相続人が誰であるかは課税の有無には直接影響しません。
| 課税の判断基準 | 被相続人の国籍と法律上の住所(Domicile) |
| 基礎控除 | 巨額な控除額(後述) |
日本の課税範囲をを左右する10年ルール
相続税の「10年ルール」は、被相続人と相続人の居住歴や国籍によって課税範囲が複雑に変動します。特に、海外に資産を持つ方や海外在住の方などは、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
アメリカ国籍者がに適用される遺産税の基礎控除と留意点
アメリカ国籍を有する被相続人については、連邦遺産税において比較的大きな基礎控除額(非課税枠)が設けられています。
非課税枠(約1,361万ドル)が適用されるための前提条件
2024年現在、アメリカ国民(U.S. Citizen)には約1,361万ドル(約20億円超、為替による)という非常に大きな基礎控除額が適用されます。この金額までは遺産税はかかりません。
【住所(Domicile)に関する重要な考慮事項】
① アメリカ国籍者は世界中どこでも控除対象
アメリカ国籍をお持ちの方(Citizen)は、日本に居住していても、高額な基礎控除(約20億円)を満額利用できるのが原則です。日本に住んでいるから控除が減額される(非居住者扱いで6万ドルになる)ということは原則としてありません。
② 富裕層にとって重要となる住所(Domicile)に関する検討事項
では、なぜ住所(Domicile)が重要なのか?それは、連邦遺産税とは別に州遺産税(State Estate Tax)のリスクがあるからです。
アメリカの住所(Domicile)は、単なる居住地ではなく本拠地を指します。 もし、資産家である被相続人が、税金対策や別荘維持のためにアメリカの住所を残していた場合、IRSや州税務当局から本拠地(Domicile)はまだアメリカ(特定の州)にあると認定される恐れがあります。
一部の州(ニューヨーク州やハワイ州など)では、連邦税よりも低い基礎控除額(例:数百万ドル)を設定しており、 連邦税はゼロでも州遺産税だけで多額の納税が発生する可能性があります。
連邦税の基礎控除を満たしていても、州の課税リスクは別途存在するため、日米どちらにDomicileがあると判定されるか(州税のリスクはないか)を専門家に確認することが、資産を守る上で非常に重要です。
Form 706(米国遺産税申告)の提出義務と期限について
米国の遺産税においては、税額の有無にかかわらず、申告手続そのものが重視される点に注意が必要です。
特に日本の相続税制度と期限や考え方が異なるため、誤解による手続漏れが生じやすい分野です。
①納税額がゼロでも申告義務が生じる場合がある
遺産総額がその年の申告基準額(Filing Threshold)を超える場合、最終的に基礎控除等により納税額が発生しないケースであっても、Form 706(米国遺産税申告書)の提出が必要となります。
「税金が発生しない=申告不要」ではありません。申告を行わない場合、無申告扱いとなる可能性があります。
② 提出期限は死亡日から9か月以内
米国遺産税申告の提出期限は、被相続人の死亡日から9か月以内です。
(※ 申請により6か月の延長は可能ですが、原則は9か月)
日本の相続税申告期限(10か月)よりも1か月早いため、
日本の手続きスケジュールのみを前提に進めると、期限超過となるおそれがあります。
③ 期限後申告による主な不利益
期限内に申告が行われなかった場合、次のような不利益が生じる可能性があります。
- 申告義務違反としての指摘
- 本来利用できた制度(例:配偶者への控除枠の引継ぎ〔Portability〕)が適用できなくなる
- 場合によっては加算税・延滞税の対象
そのため、日本側の相続手続と並行して、早期に米国申告の準備を進めることが重要です。
日米間の二重課税を調整する「外国税額控除」
日本と米国の双方で相続税・遺産税が課される場合、一定の条件のもとで外国税額控除を用いて二重課税を調整することが可能です。
課税の優先順位(基本的な考え方)
日米租税条約の規定に基づき、資産の種類ごとにどちらの国が優先的に課税するかが定められています。
例えば、不動産は所在地国優先課税が原則であり、その所在地にある国で課税された税金を、もう一方の国で控除する形になります。
- 日本の不動産: 日本で課税された相続税を、アメリカの遺産税から控除。
- 米国の不動産: アメリカで課税された遺産税を、日本の相続税から控除。
この計算と調整を誤ると、控除が適切に適用されない可能性があります。
【富裕層向け事例】国際相続の実務上のポイント
失敗事例:日米の専門家連携不足により調整に時間を要したケース
【状況:日米で専門家を個別に選任したケース】
日本側および米国側でそれぞれ別の専門家に依頼した結果、相互の情報共有や調整が限定的なまま申告手続が進行した。
日本側専門家は米国の相続・遺産税制度や英語での実務対応に十分対応できず、また米国側専門家も日本の相続税制度や評価実務への理解が限定的であったため、両者間の調整や意思疎通に相当の時間を要した。
【結果:実務調整に時間を要した】
【教訓】
国際相続では、日米両方の税制を理解し、現地の専門家と直接連携できる司令塔(バイリンガルな日本の税理士事務所)を選ばないと、現場が混乱します。
成功事例:生前対策(贈与や信託)による相続手続きの迅速化
【対策:生前に米国信託(トラスト)を活用】
生前に「米国信託」を設定し、米国の資産を信託財産として整理しました。 信託を利用することで、亡くなった後は裁判所の関与を待つ必要がなく、あらかじめ指定した承継人が、信託契約に基づいて資産の手続きを進められるよう準備しました。
【結末:円滑な送金と期限内の納税】
相続発生後、裁判所を通さずに現地の金融機関等で手続きが進められたため、比較的スムーズに資金を動かすことができました。
- 期限内の送金: 日本の相続税の納期限までに、米国から納税資金を送金。
- 附帯税の回避: 期限内に現金納付を完了したことで、延滞税などの発生を防止。
- 事務負担の軽減: 現地での複雑な裁判手続きを回避でき、ご遺族の負担を抑えて承継を完了しました。
【教訓】
国際相続では「税額を抑える」ことだけでなく、「納税資金を期限内に準備できる状態にしておく」ことが重要です。生前に信託等の仕組みを整えておくことが、結果として円滑な納税につながります。
まとめ:国際相続で最初に行動すべき3つのステップ
米国籍の方の相続では、初期対応のタイミングがその後の手続きに影響します。
混乱を避けるため、まずは以下の3つのポイントを早めに確認することが重要です。
STEP 1:死亡日から9ヶ月後の日付を確認
日本の申告期限(10ヶ月)より、米国の期限(9ヶ月)の方が早いです。 この1ヶ月の差がペナルティの引き金になります。まずは期限を把握し、スケジュールを逆算してください。
STEP 2:相続人の居住歴(10年ルール)を確認
過去10年の居住歴によって、日本で課税される財産の範囲(全世界か、国内のみか)が決まります。納税額に直結するため、初期段階での判定が必須です。
STEP 3:日米両国で連携可能な専門家の確保
これが最も重要です。二重課税や評価額のズレを防ぐためには、日米双方の税制を理解し、現地の専門家と連携できる国際税務に強い税理士を速やかに選んでください。
【国際相続は時間との戦いです】
私たちは、富裕層の皆様の国際相続において、安心と資産保全を実現するための専門チームです。
「何から手をつければいいか分からない」という方は、手遅れになる前に無料相談にて状況をお聞かせください。
資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。
お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。
豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。